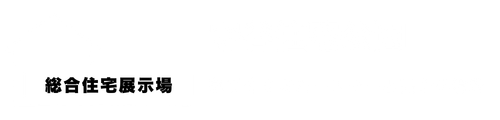未来の住まいは「時短×省コスト」が主役!2025年に建てたい理想の家7選、建築のプロが教える最新トレンド#column
この記事を読めば分かること
- 2025年に注目されている7つの住宅デザインと間取りの特徴が分かります
- それぞれのトレンドが人気の理由と実際の生活での活用方法が理解できます
- 家づくりで「時間対効果」と「コストパフォーマンス」が重視される背景が分かります
- 自分のライフスタイルに合わせた、トレンドの取り入れ方が見えてきます
- 2025年から始まる省エネ基準の義務化と新しい補助金制度について知ることができます
はじめに
夕暮れ時、仕事から帰った田中さんは玄関のドアをスマホで開け、土間スペースに荷物を置きました。「ただいま」と声をかけると、リビングの照明が自動的に点灯します。一つの階に家族の居場所がコンパクトに配置された平屋の家。キッチンから洗濯室、収納まで一直線につながる効率的な動線。壁と一体化した造作家具が、空間を美しく彩っています。
これが2025年、多くの人が憧れる理想の住まいです。
家を建てるということは、単なる箱を作るのではなく、あなたとあなたの家族の生活スタイルをデザインすることです。何十年と暮らすことになる家だからこそ、今の流行を取り入れながらも、長く快適に過ごせる工夫が必要です。
物価の上昇や建築コストの高騰、そして法律の改正など、2025年の家づくりを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな時代に、どんな住まいを選ぶべきなのか、最新のトレンドから探ってみましょう。
時間もお金も大切に!2025年住宅トレンドの核心は「効率性」にあり
初夏の心地よい風が吹く建築展示場。ベテラン建築士の佐藤さんは、新しい住宅モデルを指しながらこう語りました。「今の時代、人々が家に求めているのは『効率』なんです。時間の効率、お金の効率、そして空間の効率。この3つの効率を高めた家が、2025年のトレンドになっています。」
「タイパ」と「コスパ」という言葉を聞いたことがありますか?「タイパ」は「時間対効果」、「コスパ」は「コストパフォーマンス」の略です。簡単に言えば、使った時間やお金に対して、どれだけ満足できるかという考え方です。
物価高が続く今、家づくりにおいてもこの考え方が重視されています。2025年のトレンドランキングを見ると、この「効率」を追求した住まいが上位を占めていることが分かります。では、具体的に人気の住まいスタイルを見ていきましょう。
1. 「暮らしやすさ最優先」の平屋が不動の人気!階段なしの生活で家事も介護も楽々
朝の光が差し込む広々としたリビング。キッチンでは母が朝食の準備をし、リビングでは父が新聞を読んでいます。小学生の娘は自分の部屋から出てきて、すぐにリビングに合流。一つの階に家族の生活空間がすべて集まっています。
「2025年も平屋人気は続く」と語るのは、住宅メーカーの木村さん。2010年代後半から少しずつ人気が高まり、2022年以降は建てられる数も増加傾向にあります。その魅力は何でしょうか?
平屋の最大の魅力は「すべてが一つの階にある」という単純明快さです。階段の上り下りがないので、小さな子どもから高齢者まで、どの世代にとっても安全で快適です。将来の介護のことを考えると、この点は大きなメリットになります。
また、家事の動線もシンプルになります。掃除機をかけるにも、洗濯物を運ぶにも、一つの階で完結するので体力的な負担が少なく、時間も短縮できます。
さらに、建物をコンパクトにまとめやすいので、建築費用も抑えられます。宮崎市のような比較的土地が安いエリアでは、この「コンパクトな平屋」の人気がますます高まると予想されています。
幅広い世代が快適に暮らせる平屋は、長い目で見たときの「タイパ」も「コスパ」も優れた住まい方と言えるでしょう。
2. 「自分時間を大切にする」ヌックで心の充電!リビングにいながらプライベート空間を確保
日曜の午後、家族がリビングでくつろいでいる中、父は窓際の小さなコーナーで読書に没頭しています。そこには一人掛けの椅子と小さな本棚、そして明かりがあるだけの小さなスペース。しかし、そこは父にとって特別な「自分だけの場所」なのです。
「ヌック」とは、キッチンの横やリビングの片隅に設ける小さな空間のことです。書斎や趣味部屋を別に作るよりも面積を取らないので、建築費用も抑えられます。まさに「スペースパフォーマンス」に優れた空間と言えるでしょう。
ヌックの魅力は、家族がいる空間と完全に分かれていないこと。家族の気配を感じながらも、ほんの少し「自分だけの時間」を楽しめるのです。
デッドスペース(使い切れていない空間)を活用できるだけでなく、リビングにメリハリが生まれ、空間が豊かになります。「一人になりたいけど、完全に離れたくない」という現代人の微妙な心理に合った空間なのです。
テレワークが増えた今、ちょっとした仕事スペースとしても活用できます。完全な書斎を設けるほどではないけれど、集中できる場所が欲しい人には最適な選択肢です。

3. 「洗って干して畳んでしまう」が一直線!ランドリールームで家事時間を大幅削減
朝の慌ただしい時間。佐々木さんは洗濯機から取り出した洗濯物を、すぐ横の物干しスペースに干していきます。昨日干した乾いた洗濯物は、物干し場所の隣にあるカウンターで手早くたたみ、その横の収納棚に入れていきます。洗濯物を持って家中を移動する必要はなく、一か所で家事が完結します。
「洗う→干す→畳む→収納する」という一連の流れをスムーズにするために、ランドリースペースを設ける家庭が急増しています。洗濯機のすぐ横に物干しスペースがあれば、重い洗濯物を持ち運ぶ負担がなくなります。
さらに畳むためのカウンターや収納スペースまであれば、洗濯に関わるすべての作業が一か所で完結します。これにより家事の時間が大幅に短縮され、自分の時間を増やすことができるのです。
特に人気なのが、キッチン、浴室、脱衣所、ランドリースペースを円を描くように配置する「回遊動線」。家事をしながら家中を何度も往復する必要がなくなるので、効率がグンとアップします。
仕事と家事の両立に忙しい現代人にとって、このランドリースペースは「タイパ」を大幅に向上させる重要な要素となっています。
4. 「もうバルコニーは必要ない」バルコニーレスで掃除も維持費も節約!室内干しで天候を気にしない生活
冬の寒い日。外は強い風が吹いていますが、鈴木家では洗濯物を室内の物干しスペースに干しています。天気を気にする必要もなく、外からの目も気にならず、いつでも洗濯ができる快適さです。外を見ると、家の外観はバルコニーがない分、すっきりとしたデザインになっています。
ランドリースペースの普及と共に増えているのが「バルコニーを作らない家」です。室内に物干しスペースや乾燥機があれば、わざわざ外に洗濯物を干す必要がなくなります。
バルコニーレスの最大のメリットは、天候に左右されない生活です。雨の日はもちろん、花粉シーズンやPM2.5が多い日でも、気にせず洗濯物を干すことができます。また、洗濯する時間帯も自由。夜中や早朝でも、近所の目を気にせず洗濯物を干せます。
建築費用や維持費の面でも大きなメリットがあります。バルコニーを作らない分、初期費用が抑えられるだけでなく、将来的なメンテナンス費用も削減できます。さらに、バルコニーの掃除という面倒な家事からも解放されるのです。
これらの理由から、バルコニーレスは今や「スタンダードな選択肢」になりつつあります。効率的な生活を求める現代人にとって、理にかなった選択と言えるでしょう。
5. 「地震でも家具が倒れない」造作収納で安全と美しさを両立!あなた専用の収納スペース
新築の松本家では、リビングの壁一面が本棚になっています。しかし、それは後から置いた家具ではなく、家を建てる時に壁と一体で作られた「造作収納」です。家の雰囲気に完璧に調和し、まるで建物の一部のような美しさです。大きな地震が来ても、この収納が倒れる心配はありません。
「造作収納」とは、収納するものやスペースに合わせて、建物と一体でつくる収納家具のこと。後から購入する既製品の家具と違い、空間にぴったり合わせて作れるので、無駄なスペースがなく、デザイン的にも統一感があります。
最大の利点は安全性です。家具が壁や床にしっかりと固定されているので、地震の際に家具が倒れて怪我をする心配がありません。子どもがいる家庭や高齢者と暮らす家庭では、この安全性は大きな価値があります。
また、空間を無駄なく使えるので、限られた面積でも十分な収納量を確保できます。さらに、家の雰囲気に合わせたデザインにできるので、インテリアの統一感も生まれます。
宮崎住宅建設工業では、収納だけでなく、机や洗面台なども、スペースや使い方に合わせて職人が現場で作り上げています。既製品では得られない、あなただけのオリジナル空間を実現できるのです。
6. 「声やスマホで家をコントロール」スイッチレス住宅で未来型の暮らし!テクノロジーが支える快適生活
仕事を終えて帰宅する前に、山田さんはスマホで自宅のエアコンをオンにします。家に着くと、玄関前でスマホをかざすだけでドアが開きます。「ただいま、照明つけて」と声をかけると、リビングの明かりがついて、お気に入りの音楽が流れ始めます。夜寝る前には「おやすみ」と言うだけで、家中の電気が消え、エアコンの温度が調整されます。まるで未来の家のような暮らしが、今実現しています。
「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」住宅とは、ITやAIを使って暮らしをよりスマートにする住宅のこと。インターネットに接続された機器を通じて、家電や設備をスマートフォンや音声で遠隔操作できます。
具体的には、ロボット掃除機やスマートスピーカー、スマホで鍵の開閉ができる玄関などが代表例です。これらのテクノロジーを活用することで、生活がより快適で便利になります。
最近特に注目されているのが、住宅内のエネルギー管理システム「HEMS(ヘムス)」との連動です。電気や水道の使用量を見える化したり、使いすぎる時には自動で制御したりすることで、省エネにも貢献します。
忙しい現代人の生活をサポートする技術として、このIoT住宅は今後ますます普及していくでしょう。テクノロジーを味方につけた快適な暮らしを実現したいあなたに、ぴったりの選択肢です。
7. 「室内なのに自由な使い方」土間スペースで家族の創造性が広がる!多目的に使える特別な空間
週末の午後、高橋家の土間スペースは家族の活動で賑わっています。父親はDIYで棚を作り、母親は広い空間で大きな布を広げて洋服を作っています。子どもたちは友達を呼んで、思い切り遊んでいます。靴を脱がなくても良いので、出入りも自由。外と内の中間のような開放的な空間が、家族の創造性を刺激しています。
コンクリートやモルタル、タイルで仕上げた「土間」は、室内でありながら屋外のように使える特別な空間です。靴のまま入れて、多少汚れても気にならないので、さまざまな活動に適しています。
コロナ禍以降、「おうち時間を充実させる場所」として人気が急上昇した土間。物置、遊び場、DIYスペース、セカンドリビング、来客スペースなど、使い方は無限大です。
特定の用途に固定されず、その時々の家族の状況や必要に応じて自由に使えるフレキシブルさが魅力です。家族構成やライフスタイルが変わっても対応できるので、長い目で見た時の「タイパ」も「コスパ」も優れています。
創造的な活動や家族の交流を大切にしたいあなたには、この土間スペースが新たな可能性を広げてくれるでしょう。
2025年から「省エネ住宅」が義務に!新基準と補助金制度でエコな家づくりが加速
真夏の暑い日でも、この家の中は心地よい涼しさ。厚い断熱材と高性能な窓が、外の熱気を遮断しています。冬は暖かく、夏は涼しい。そして太陽光発電システムのおかげで、電気代もぐっと抑えられています。環境にも家計にも優しい「省エネ住宅」が、これからの標準になります。
上位7つ以外のトレンドとして注目されているのが「省エネ住宅」です。快適さや環境への配慮から人気を集めてきた省エネ住宅ですが、2025年4月からは「省エネ基準への適合」が義務化されました。
これまで最高等級と言われていた断熱等級4、一次エネルギー消費量等級4が、2025年からは「標準レベル」になったのです。さらに2030年までには、より高い省エネ性能を持つZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準まで基準が引き上げられる予定です。
また、2025年の補助金制度「子育てグリーン住宅支援事業」には、長期優良住宅やZEH住宅よりもさらに省エネ性が高い「GX志向型住宅」が新たに加わりました。
これらの変化により、省エネ住宅は今や「選択肢」ではなく「必須」になりつつあります。初期費用は少し高くなるかもしれませんが、長い目で見れば光熱費の削減により、総合的なコスパは優れています。
地球環境のことを考えると同時に、将来の家計への負担を減らしたいあなたには、高い省エネ性能を持つ住宅を検討する価値があるでしょう。
まとめ:トレンドを知り、自分らしい家づくりをしよう
晴れた春の日、完成した新居の前で鍵を受け取る中村さん一家。ベテラン建築士の井上さんは笑顔でこう言いました。「この家には最新のトレンドを取り入れながらも、中村さん家族だけのオリジナリティがあります。長く快適に暮らせる家になりましたよ」
服の流行と同じように、住宅のトレンドも時代とともに変わっていきます。トレンドは「その時代に合っている」「多くの人に支持されている」という証拠ですから、上手に取り入れることで、より快適な住まいを実現できます。
しかし、トレンドだけを追いかけると、自分の生活スタイルに合わず、使いづらさを感じることもあります。また、時間が経つと好みや家族構成が変わることもあるでしょう。
真に満足できる家を建てるためには、自分や家族のライフスタイルや価値観をしっかり考え、「何を取り入れて、何を取り入れないか」を判断することが大切です。
完全自由設計の宮崎住宅工業では、トレンドを適所に取り入れつつも、長い年月が経っても心地よいと感じられる住まいづくりを心がけています。2025年からの家づくりを考えているあなた、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。