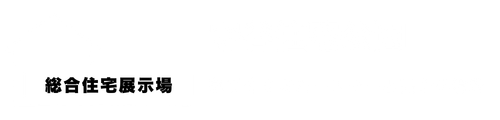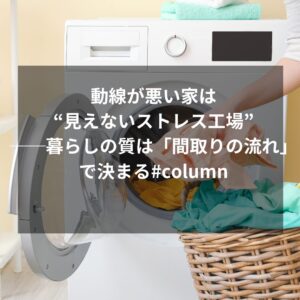収納スペースが多いと暮らしやすい?実はそれ、落とし穴かもしれません#column
この記事でわかること
- 「収納たっぷり=便利」が通用しない理由とは?
- 実際の家づくりで起こった“配置ミス”の体験談
- 家事動線と収納の最適なバランスのとり方
- モデルハウスでしか感じられない収納の“リアル”とは?
◆「収納は多いほど安心」…それ、思い込みかも?
新しい住まいを計画するとき、多くの人がこう言います。「とにかく収納はたくさん欲しい」と。でもちょっと待ってください。収納は“多さ”よりも“置き方”と“使い方”が重要なんです。
むやみに数を増やすことで、かえって動線が複雑になったり、使いにくさを生んでしまうケースも少なくありません。収納は“しまう場所”であると同時に、“暮らしを動かす導線”の一部。配置を誤ると、その快適さを一気に損なってしまいます。
◆ケーススタディ:詰め込みすぎた結果、暮らしにくくなった家
東京都郊外で家を建てた40代の三浦さんご夫婦。子育て真っ最中ということもあり、「収納はたっぷり用意しておこう」との思いで、間取りに収納スペースをふんだんに盛り込みました。
- シューズクロークに2畳
- リビング横にウォークイン収納
- キッチン脇には食品庫とは別にストックルーム
- 子ども部屋には各自クローゼット+本棚
- 階段下にも全面収納を設置
当初は「これで安心」と思っていたそうですが、いざ住んでみると違和感が…。
「収納のために通りづらい場所が増えた」
「結局、奥の方は全然使ってない」
といった“もったいない空間”がいくつも生まれていたのです。
◆「安心のための収納」が生活の足かせに?
多くの収納を設けた家でよくあるのが、「しまっているけれど使っていない」アイテムの山。
収納が多すぎることで、「とりあえず取っておく」ものが増え、結果的に空間が圧迫され、家の中が重たく感じるようになります。
さらに問題なのは、収納スペースが生活の動線に食い込んでしまうケース。
たとえば、
- リビングから洗面所へ向かう廊下に大型収納を設置してしまい、家族がすれ違うたびにストレスを感じる
- キッチン背面に大容量の棚を作りすぎて、冷蔵庫の前が狭くなった
など、「便利なはずの収納が、暮らしのジャマになる」矛盾が起きてしまうのです。
◆図面では見えない「違和感」は、体感して初めてわかる
設計段階では気づけない不便さって、実はたくさんあります。
「この収納、本当に使うの?」「動線の流れが不自然じゃない?」という疑問は、図面上では気づきにくく、実際に“歩いてみて”初めて見えてくるものなんです。
そこで重要なのが、モデルハウスでの“収納チェック”。
モデルハウスを見学する際、以下のような観点で見てみましょう:
- 収納のドアを開け閉めしてみる(動線との干渉をチェック)
- 実際にそこに物を入れるイメージが湧くか?
- 奥行きが深すぎたり、取り出しづらい設計になっていないか?
3〜5軒ほど見て回ると、「自分たちに合った収納」の輪郭がくっきりしてきます。

◆収納で失敗しないための黄金ルール3つ
注文住宅での収納設計を成功させるためには、次の3つのポイントを意識しましょう。
1. 「何を入れるか」を明確にしてから設計を
ただの空きスペースではなく、「ここには掃除機、ここには子どもの文具」と、収納の中身を想定することでムダを防げます。
2. 動線の流れを第一に考える
収納が通路や作業エリアの邪魔をしていないか、暮らしの“流れ”を意識して配置するのが大切です。
3. モデルハウスで“リアルな使い方”をシミュレーション
実際に見て、動いて、「ここに何を置くか」を体で感じてください。紙の間取り図では見えない違和感が必ずあります。
◆まとめ:収納は“住み心地”を左右するパーツ
収納は、ただ空間を整えるためだけのものではありません。日々の暮らしをスムーズにし、動線を支える役割があります。
「とにかくたくさんあれば安心」という感覚を一度疑い、本当に必要な場所に、必要な量を確保することが、後悔のない家づくりへの近道です。
あなたの新しい暮らしが、より快適なものになるように。ぜひ展示場へ足を運び、“収納の本当の役割”を、自分の目と体で確かめてみてくださいね。