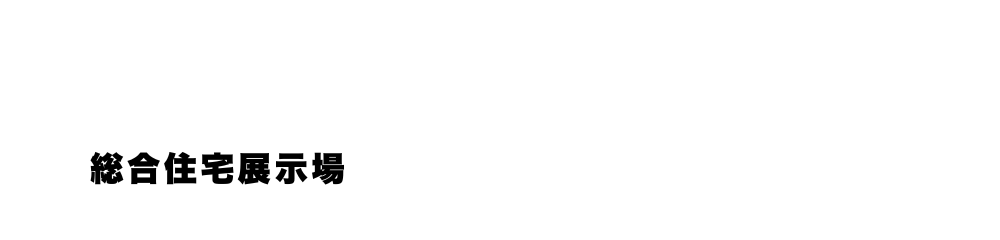“災害なんて来ない”と思っていた家庭が、たった週末1時間の準備で“避難も生活も安心”になった!家族で始める6つの防災習慣#column
この記事を読めば分かること
- 防災が“特別なこと”ではなく、暮らしに溶け込む習慣になる理由
- 避難場所の決め方と家族会議の進め方
- 紙のハザードマップを使ったリアルな避難ルート確認のやり方
- 保存食を「食べて減らして補充する」ローリングストック術
- 家具の配置や固定で“安全な家”に変えるコツ
- 防災グッズや非常用バッグを“普段も使える便利アイテム”に変える工夫
はじめに
ある週末、何気なく見ていたニュースで「災害時に家族と連絡が取れず、不安なまま避難した人」の体験談を耳にしました。
その瞬間、あなたも「うちは大丈夫だろう」と思っていた気持ちがぐらつくかもしれません。
防災の準備は「面倒」「難しそう」と思われがちですが、実は暮らしに楽しく取り入れる方法があります。家族で会話をしながら、遊びや普段の生活に混ぜるだけで、自然と“いざ”に備えられるのです。
この記事では、あなたの家を「安心の拠点」に変える6つの工夫を紹介します。

1. 家族会議で“避難ルール”を共有する
夜、リビングに家族が集まって「もし地震がきたらどこに集合する?」と話し合う光景を想像してください。
普段はゲームの話で盛り上がる子どもたちも、このときばかりは真剣な顔に。
例えば「公園の入り口の時計台」を集合場所に決めておくだけで、連絡が取れないときの安心につながります。家族会議そのものが「防災教育」にもなり、子どもが主体的に考えるきっかけになるのです。
2. 紙のハザードマップで“歩いて確認”する
スマホの地図は便利ですが、停電や通信障害で使えなくなることがあります。
だからこそ「紙のハザードマップ」を壁に貼り、家族でルートを確認することが大切です。
休日に「今日は防災探検だ!」と声をかけて、実際に避難場所まで歩いてみましょう。途中で「ここは狭いから危ないね」「ここは街灯が多いから夜も安心」と、気づきがたくさん生まれます。遊びながら覚えたルートは、非常時にも自然と体が動く“命の地図”になります。
3. 保存食は“楽しみながら回す”ローリングストック
乾パンだけが非常食ではありません。
普段の食事に使えるレトルトカレーや缶詰、スナック菓子を常備し、「食べたら買い足す」を繰り返すのがローリングストックです。
例えば「月に一度の非常食デー」を家族で決めて、「今日は災害ごっこご飯」として食べる。おいしい、便利、飽きない保存食を選べば、防災も食育の一部になります。
4. 家具の配置を変えるだけで“命を守れる”
防災と聞くと特別なグッズばかりを想像しますが、実は家具の配置こそが命を守る最前線です。
寝室に大きな本棚を置いていませんか?
地震で倒れれば、避難どころか命にかかわる危険になります。
家具を壁に固定する、通路をふさがないように置く、頭の上に落ちるものを置かない——この3つを見直すだけで、家は“安全なシェルター”に近づきます。
5. 防災グッズを“日常でも使えるもの”にする
懐中電灯やポータブル電源を防災だけに閉じ込めておくのはもったいない。
キャンプやベランダでのバーベキュー、停電時のちょっとした明かり取りにも使えます。
「普段から触れること」で子どもも自然に使い方を覚え、「停電しても大丈夫」と自信につながります。防災グッズを“生活の便利アイテム”として活用すれば、防災のハードルはぐっと下がります。
6. 非常用バッグは“家族ごとにオーダーメイド”
非常用バッグは一度作って終わりではありません。
赤ちゃんがいればミルクやオムツ、小学生には好きなお菓子や小さなおもちゃ、年配の家族には常備薬を。
年齢やライフスタイルの変化に合わせて中身を定期的に入れ替えることで、本当に役立つ“命のバッグ”になります。
地震直後、家族はそれぞれ別の場所にいた。
でも数時間後、公園の時計台の下で再会できた瞬間の安堵感。
バッグから取り出したチョコレートを分け合いながら、「準備しておいてよかったね」と笑い合う姿。
そんな未来を描けるのは、今日のあなたの小さな行動からです。
まとめ
- 防災は「特別なこと」ではなく「日常の習慣」にできる
- 家族会議で集合場所やルールを決める
- 紙のハザードマップを使い、実際に避難ルートを歩いて確認する
- 保存食はローリングストックで「楽しみながら備える」
- 家具の配置や固定を見直して安全な家にする
- 防災グッズや非常用バッグは家族に合わせて進化させる